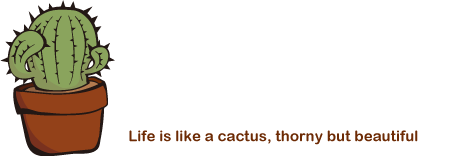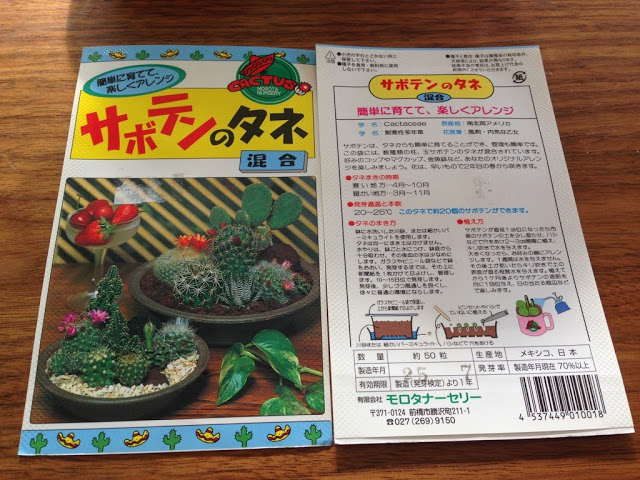※本記事に関しましてはいろいろご意見を頂戴しております。とりあえずのところ、こんな話もあるのね、ぐらいのコラムとしてお読み下さいませ。
一般に、サボテンは1時間でも1分でも1秒でも多く日光を当てなさいと言われています(一部の森林性サボテンなどを除く)。
なんでこんなことを言われているのでしょうか。
サボテンは炎天下の砂漠で育っているイメージがあるからでしょうか。
日陰においておいたら徒長させてしまったという経験則からでしょうか。
・・・
さて、サボテン科はCAM型植物と言われています。
CAM型植物とはCAM型光合成を行う植物です。
CAM型光合成とは、超端的にいうと、「二酸化炭素の取り込みを夜に行ってリンゴ酸を生成、そのリンゴ酸を昼まで液胞に貯蔵し、昼に還元するような光合成」のことです(詳しくはCAM型光合成 – Wikipedia)。
この特殊な光合成のおかげで、昼間に気孔を開く必要がなくなり、サボテン科は灼熱や乾燥に耐えられるらしいです。
しかしながら、CAM型光合成は普通の光合成(カルビン-ベンソン回路のみの光合成)よりエネルギーを必要とし、さらに吸収できる二酸化炭素量もリンゴ酸を貯蔵する液胞の量に依存するわけですから、一般の光合成を行う植物よりも成長は遅くなります。
・・・
というふうに言われていますが、すべての二酸化炭素が夜に吸収されてリンゴ酸に貯蔵されるかというと、そうではなく、一部の(専門用語で、CAM型光合成のphase 4(明期後半)の時に吸収された)二酸化炭素は、リンゴ酸を経由せずに、C3植物のようにカルビン-ベンソン回路に直接使用されるそうです。
この仕組は、上述のようにリンゴ酸の貯蔵量には限界が有るためで、それを昼間に使いきってしまったときに、仕方なく外部から二酸化炭素を取ってくるというイメージでよいと思います。故にこの吸収は明期の後半におきるわけです。
・・・
ということは、サボテン科の物質生産性を高める一つの方法は、この明期後半(≒昼)の二酸化炭素吸収量をいかに増やすかにかかっているわけです(先に述べたように、夜間の二酸化炭素吸収量は液胞の許容量に依存するためどうしようもないのです)。
・・・
では、その明期の二酸化炭素吸収量をいかに増やすかということなのですが、とりあえず
「より多くの時間、日光を当てる(昼を長くする)」という方法が考えられます。
目長がCAM性に及ぼす影響をみると,長日,短日,自然日長各条件下において,昼間の平均光強度の上昇とともにCAM性は低下し,昼間の総光量が200cal/cm2/day以上の光条件下で定常値に達する。各日長条件下で得られた定常値を比較すると,長日条件下では40%前後の低いCAM性を示し,日長が短くなるにつれてCAM性は増大し,短日条件下では80%前後の値を示していた。さらに,1日当りのCO2収支は,CAM性の高い短日条件下で大きく,200cal/cm2/day以下の光量下において,長日条件との差は約2倍の値になっていた。~中略~パインアップルの物質生産機構が有利に展開されるであろうと予想した,長日条件や高窒素条件下において,CAM性の動きは予想とは全く逆の反応を示していた。日長条件や窒素条件によって1日当りのCO2収支を増大させる現象は,CAM性の強化をともなって生じた。光強度や土壌水分条件のような,パインアップルのCAM型光合成に対し即時的に作用するような要因においては,パインアップルの物質生産を増大させるための方策として,そのCAM性を打破するような制御が有効なものと考えられる。しかし,日長や窒素条件のような,CAM型光合成の本質的な部分に関る要因については,パインアップルの物質生産を増大させるためには,そのような要因を通してCAM性を強化し,夜のCO2吸収を活性化するような方向で制御を加えることが有効なものと考えられる。