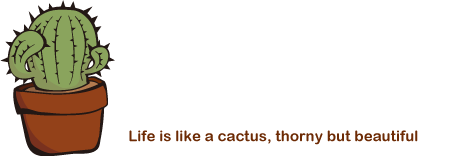カイガラムシ・アカダニのような害虫や、CVXのようなウイルス、赤腐れ病や南米病などの病気、日焼けや凍傷、やたらと鉢を倒すおてんばキャットや、やたらと刺に引っかかる窓のカーテンなど、たくさんあるわけですが、我が家の一番最強の天敵は、そう。。。
・・・
集合住宅に住まれていない方に大規模修繕についてご説明しますと、大規模修繕というのはマンションなどが15年ぐらいに1度、外壁やバルコニーなどを一斉に点検・修繕するというイベントです。普段バルコニーとかに出している植木とかを、そのイベント中はどうにか別の場所(ふつうは家の中)に置いておかなければならないというものです。
ちなみにマンションによっては、このイベント用に共有の植栽置場とかも一時的に用意される場合もあります。
実は我がマンションでも植栽置場は用意されたのですが、バルコニーにある大量のサボテンをそこに置くわけにもいきませんでした。
理由としては、まず量はもちろん多いですし、サボテンやアガベの刺はとても危険ですので、もし植栽置場に置いたとして、マンション内の少年少女達が間違って触って怪我でもしたら、今後一生「6階のサイコパスサボテン野郎」として、マンション内で後ろ指を指されることになるのは目に見えてます。うしろゆびさされ組です。ですから、植栽置き場は当てにできません。
※
また、こういう大規模修繕のときなど、植物を預かっていただける、いわゆるペットホテルの植物版みたいなサービスもWEBで検索する限りあるようなのですが、結構お値段もかかるようなのと、やはり植物自体が特殊気味ということで今回は見送りました。
というわけで、いろいろ考えたのですが植物を全部部屋の中に入れることになりました。4ヶ月強。
↓写真は家の中に入れた植物の「一部」です。
大規模修繕を恐れる最大の点は、部屋に入れることによる日照不足です。
植物を部屋に入れるだけでも光激減なのですが、さらに大規模修繕では、マンション全体が黒っぽい布みたいなので囲まれます。しかも金属の足場がジャングルジムのように組まれ、日陰が多くなり、窓から入る光をさらに激減させます。
そして、更に都合が悪いことに、工事の際はプライバシーを保護するために、カーテンは常に締めてほしいというお願いもされています。
↓写真は家の中に入れた植物の「一部」です。
日照不足は、単純に徒長の原因になりますし(しかも徒長したらもとには戻りません)、より日照が不足すれば最悪植物は死にます。
下の写真はブロンズ姫(Graptopetalum paraguayensis f.bronz)ですが、徒長が始まっています。
徒長させないためには、成長を開始させないことが重要でしょう。
成長を開始させないための栽培の基本は断水です。干からびそうになる限界まで断水です。おそらく。いわゆる休眠状態を維持させるわけです。
というわけで可能な限り水を切っています。
休眠状態のサボテンはかなり強いです。下記の記事は休眠状態のサボテンの強さを検証したものです。

サボテンだけでなく塊根系ももちろん断水です。どうかこのまま目覚めないでくれー!といつも願っています。
ちなみに森林性サボテン(リプサリスなどのある程度の湿度がある環境のほうが良さそうで、日陰でもある程度育ちそうなもの)やビカクシダなどは絶妙な加減で水やりをしています。
ちなみに、上記の通り光激減ということで断水を前提としていますが、もちろん光は可能な限りあったほうがいいに決まっています。というわけで、意味があるかは微妙ですが、植物育成灯を導入しています。
私がいままで使っていた植物育成灯は、よくある青と赤の光の組み合わせのライトを使用していたのですが、今回はなんとなくフルスペクトル(とされている)のものに変えました。↓です。
光スペクトラムアナライザなどもちろん持っていないのですが、このライトを窓の近くで使用しているとちゃんと虫が集まってくるので、すくなくとも紫外線領域あたりは出力されているような気はしました(白いLEDは、フルスペクトルに見えてそうでないことが多いですが、これはちゃんとしているかな・・・たぶん。)。
私は植物の健全な育成には青と赤だけでなく、(特に肉厚な多肉植物には)緑色の光も必要説の信者なのですが、緑色云々を別にしても、サボテンを栽培していて最近わかってきたことが「結局のところ、人間にとって心地よい環境にしておけばサボテンは大丈夫(サボテンも心地よいはず)」なのではないかということです。気温も風通しも湿度も光も。
我々人間が「赤」と「青」の光の中でずっと生きろって言われても辛いです。目がチカチカしますし!だからサボテンも辛いんではないかと思うのです。まぁ科学的根拠ゼロなんですが。。。
ちなみに波長に関しては、過去の記事ですこし書いていますので参考まで。


・・・
ということで、導入している植物育成灯ですが、あくまで人間側の気持ちのカバーです。波長があっていようが人間が眩しかろうが、植物が健全に成長する光量としては雀の涙です(距離などにもよるとは思いますが、我が家の植物の量を考えると全く十分ではありません)。あくまでも気持ちです。それは忘れてはならないです。
あとは植物を部屋に入れる際に確保しておきたいのは、風通しでしょうか。
今回は、アイリスオーヤマさんの上下左右に風を送ることができるDCタイプのサーキュレータを使用しています。結構常時動いているので、なんとなくACではなくDC駆動のを選びました。ふるさと納税で買いました。
・・・
大規模修繕対策としてはこんなところですね。
どんなサボテン栽培書にも「大規模修繕の突破の仕方」が書かれていないので、だれか執筆してくれないでしょうかね!
ちなみに、大規模修繕が2月から6月で、最も地獄ということを書きましたが、これがもし6月から10月とかだったら、家の中が鉢や土に潜んだ虫たちで溢れたふれあい昆虫館になるところでした。しかもかっこいいカブトムシや綺麗なアゲハチョウならまだしも、ワラジムシやGやカメムシ多めのダーク昆虫館なわけです。そういう意味では、冬開始でよかった部分はあります。
あとは・・・、例えば余っている培養土や農薬なども全部部屋の中に入れる必要があり、そこらへんとても苦労しましたね。。。清潔面とか。
・・・
というわけで、最後は部屋の中でもそれっぽく咲いているなにかの写真です。
100均で昔買ったハティオラ。

昔、世界らん展でかったデンドロビウムのなにか。いい匂い。今年はコロナウイルスの影響で東京ドーム行けなかったのが残念です。
これもいつかのらん展から。ロックハーティア。
100均のリプサリスのなにか。
うーん、日光があんまり必要なさそうなのが咲いてますね。
さてさて無事大規模修繕を突破できるのでしょうか。